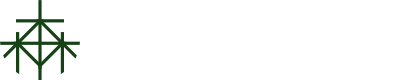林業における労働災害発生率は全産業で最も高くなっており、特にかかり木処理での作業は大変危険が伴うことからその安全性を確保することが必要不可欠です。
本記事ではかかり木処理における労働安全対策に焦点をあて、その重要性と具体的な対策について説明します。
労働安全の重要性
かかり木とは「倒した木が周りの木に引っかかっている状態」であり多くの危険要因を伴っています。
その危険は自分のみならず周りの労働者にも及ぶ可能性があります。
そのためできる限り速やかに、そして安全性を確保しつつ対応しなければなりません。
労働者の健康と生命を守るためにも、必要な労働安全対策を講じることが重要であり、このことは作業効率や品質の向上にも寄与します。
労働安全対策の具体例
適切な訓練と教育
労働者にはかかり木処理に関する適切な訓練と教育を受けさせることが重要です。
安全な作業方法や道具の使用法、緊急時の対応策などを理解させることで事故の無くしリスクを軽減することができます。
作業環境の評価
かかり木の状況を判断し作業現場の環境を評価することによりリスクを特定することが非常に重要です。
ひとりで判断できない場合は遠慮無くベテラン従事者や仲間に相談することを推奨します。
また速やかに処理できない時や一時的にかかり木を放置する場合、立ち入り禁止の処置をすることが必要です。
リスクを除去し確実に処理できる環境が整ってから必要な対応を実施することで事故を防ぐことができます。
機械と道具の使用
かかり木発生時は機械や道具を用いて対応することが先決です。
木回しに使用するフェリングレバー、けん引する場合に使用するチルホールや林業機械により、確実にかかり木を処理することが重要です。
速やかにかかり木を処理するためにもフェリングレバー等は現場に携行することが重要です。
禁止事項の徹底
法令やガイドラインにおいて、
- かかり木の放置
- かかられている木の伐採
- かかっている木の元玉切り
- 他の立木のあびせ倒し
は非常に危険な処理であることから禁止事項になっています。
禁止事項を徹底することにより、かかり木処理のリスクは大きく減少するといって過言ではありません。
まとめ
かかり木処理が危険であることは理解されつつも、かかり木が起因となる災害が毎年発生しています。
災害を起こさないためにも適切な訓練や禁止事項の徹底等の対策を実施することが求められます。
林業には「特殊伐採」という通常の伐採作業(ここでは樹木の根元から伐採することを指します)とは異なる特別な伐採方法があります。 特殊伐採が必要になる状況として、樹木の成長に伴い通行や隣接地等への障害となった場合、気象や枯損により倒木・枝[…]